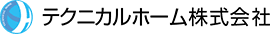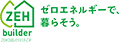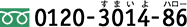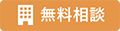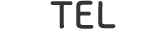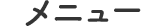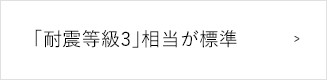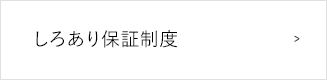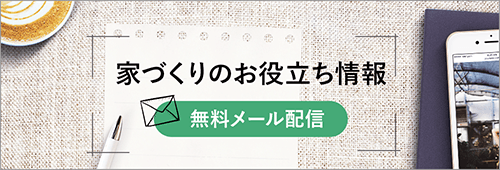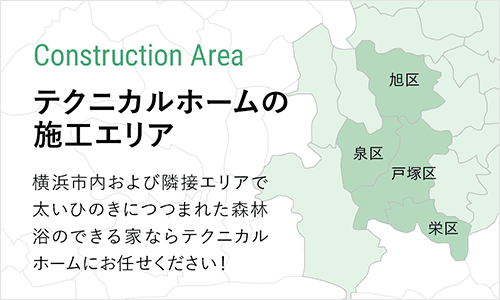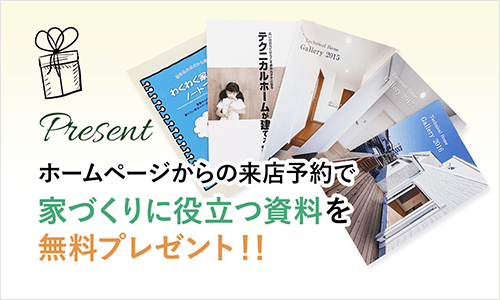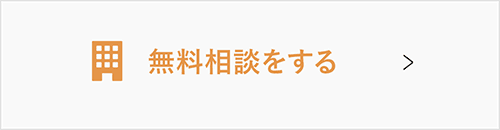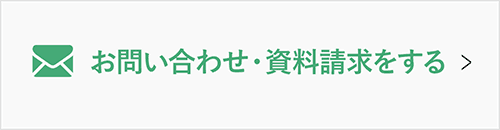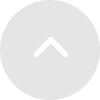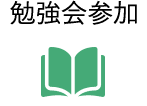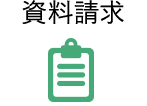後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ
【転落事故対策や侵入犯罪対策には、こんな方法もあります】
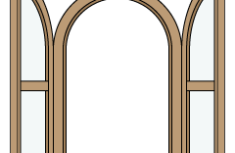
窓を開ける時間が増える時期は、子どもの転落事故が発生しやすいものです。 消費者庁の調査によると、 乳幼児の育児経験がある方の約4割が、 子育て中に転落事故の経験を経験しており、 その約3割が医 […]
【そのカセットコンロとカセットボンベの使用期限は?】
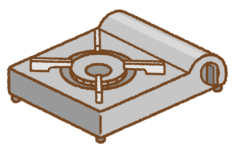
自然災害などにより停電した時、 カセットコンロとカセットボンベがあると心強いですよね。 岩谷産業の試算によると、 大人2人が1週間に必要なカセットボンベの数は、 ・気温10度のとき・・・9.1 […]
【夜間熱中症を防ぐための睡眠環境とは?】

総務省消防庁によると、 8月19日~8月25日の1週間に熱中症で救急搬送された方は、 6,711人だったとか。 このうち、発生場所の割合で30%を超えたのは、 「住居(敷地内すべての場所を含む […]
「 節電は無理の無い範囲で! 」
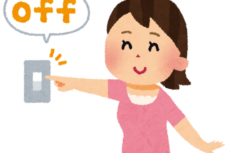
「冬の節電期間」開始から約2カ月。 政府は「無理の無い範囲で」と呼びかけていますが、 長引く電気代の高騰のため、 体調不良になるほどの節電をする方もいるとか。 ところで熱中症より凍死で亡くなる方の方が多いこ […]
【 座りっぱなしにご用心 】

2,020年に世界保健機構が発表した 『WHO身体活動・座位行動ガイドライン』によると、 18~64歳の成人が健康効果を得るには、1週間を通して 中強度の有酸素性の身体活動を少なくとも150~300分、 高 […]
【 新居でキッチンマットを使いますか? 】

みなさんのお宅ではキッチンマットを使っていますか? 「今まで特に必要性を感じていなかったけれど、膝や腰が痛くなった時、 初めてキッチンマットのクッション性のメリットに気づいた」 という方は少なくありません。 実際、医師監 […]
【 キッチンは「女性の城」にしますか?「家族の城」にしますか? 】

奥様の中には、当然ですが料理が苦手な方もいます。 料理が好きでも、忙しくて負担に感じている方もいます。 しかし、共働き世帯でさえ奥様が担当する家庭は多いものです。 みなさんのお宅はどうですか? とはいえ、ど […]
【初期費用は高くても、長期で比較すればお得になる場合もあります。】

「低価格で新築できる」 「坪単価は地域で最安」 「毎月の住宅ローンは賃貸住宅の家賃程度」 などの広告を見たことはありませんか? 住宅ローンの負担を少しでも減らしたい方にとっては、 とても魅力的なフレーズですよね。 しかし […]
[[こんなときどうするの?…フローリングの損傷]
【横浜市】の工務店 テクニカルホームの家づくりに役立つ情報 横浜で家を建てるならひのきの森® 今日は、「フローリングの損傷」についてです。 お宅のフローリングには、キズや凹みがありませんか? フローリングの損傷を放置す […]
[[こんなときどうするの?…収納スペースの結露対策]
【横浜市】の工務店 テクニカルホームの家づくりに役立つ情報 横浜で家を建てるならひのきの森® 最近、一気に寒くなってきましたね。 ホームセンターでも結露対策グッズを多く見かけるようになりましたが、みなさん […]
- 2026年2月 (7)
- 2026年1月 (9)
- 2025年12月 (9)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (9)
- 2025年9月 (9)
- 2025年8月 (9)
- 2025年7月 (9)
- 2025年6月 (8)
- 2025年5月 (8)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (7)
- 2025年1月 (9)
- 2024年12月 (9)
- 2024年11月 (7)
- 2024年10月 (9)
- 2024年9月 (8)
- 2024年8月 (9)
- 2024年7月 (9)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (9)
- 2024年4月 (9)
- 2024年3月 (9)
- 2024年2月 (8)
- 2024年1月 (9)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (8)
- 2023年10月 (9)
- 2023年9月 (9)
- 2023年8月 (9)
- 2023年7月 (8)
- 2023年6月 (9)
- 2023年5月 (9)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (8)
- 2023年1月 (8)
- 2022年12月 (9)
- 2022年11月 (9)
- 2022年10月 (8)
- 2022年9月 (9)
- 2022年8月 (8)
- 2022年7月 (9)
- 2022年6月 (8)
- 2022年5月 (9)
- 2022年4月 (9)
- 2022年3月 (9)
- 2022年2月 (8)
- 2022年1月 (8)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (9)
- 2021年10月 (9)
- 2021年9月 (8)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (8)
- 2021年6月 (7)
- 2021年5月 (8)
- 2021年4月 (8)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (9)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (9)
- 2020年9月 (9)
- 2020年8月 (8)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (8)
- 2020年2月 (7)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (9)
- 2019年11月 (7)
- 2019年10月 (9)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (8)
- 2019年7月 (8)
- 2019年6月 (8)
- 2019年5月 (9)
- 2019年4月 (9)
- 2019年3月 (9)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (7)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (8)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (9)
- 2018年5月 (9)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (9)
- 2017年12月 (9)
- 2017年11月 (5)