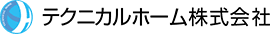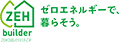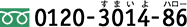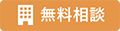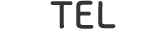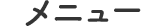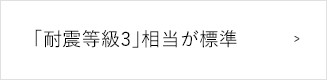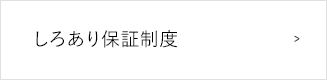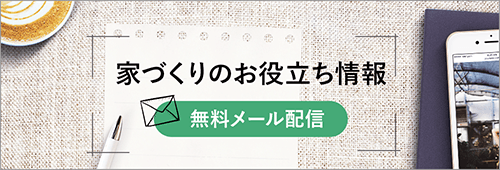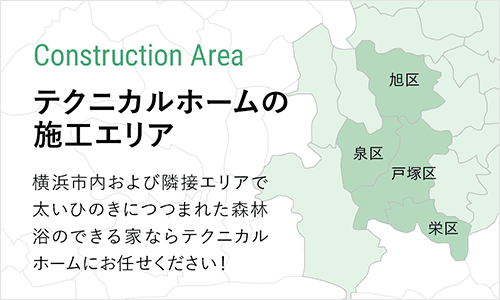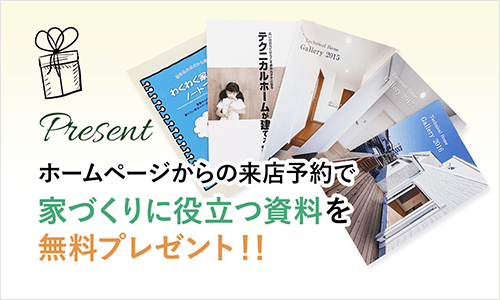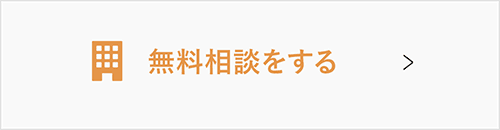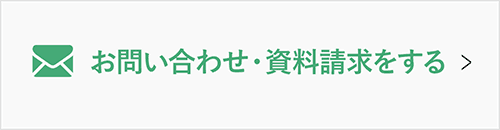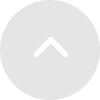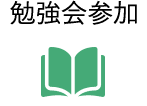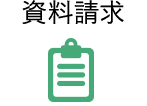後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ
「 要望を打ち合わせ対策シートにまとめましょう。」

あなたと家族の暮らし方に合う家をつくるには、 予算や要望など、多くの情報を担当者に伝えなければなりません。 そのためには、どんな家づくりをしたいのか、 新居でどのように暮らしたいのか、 イメージをできるだけ […]
【 水まわりの掃除の手間を減らすには? 】

水廻りの掃除が好きですか? 「きれいになるのが楽しいから苦にならない」 という方もいるでしょうが、 掃除が苦手な方や、慌ただしい毎日を過ごしている方は、 掃除の手間を極力減らしたいのではないで […]
【施工業者との繋がりは、引き渡し後も大切に。】

国土交通省の「平成30年 住生活総合調査結果」によると、 今後住み替える意向の有無にかかわらず、持ち家の点検の依頼先で 最も多かったのは『現住宅の施工業者』で、 次に多かったのは『入居後に自身で探した業者』 […]
【 低金利を前提とした借り過ぎに注意しましょう。 】

住宅ローンの変動金利型は、固定金利型より金利が低いですよね。 そのため、6割以上の方が変動金利型を選んでいます。 その中には、せっかく低い金利を選んだのに、 「金利を払わなくて済む分、借入額を増やそう」 と […]
「 冬の寝具の湿気・ダニ・カビ対策 」

フローリングの上に布団を敷いて寝ると、 温かい布団と冷たいフローリングの温度差により、 敷き布団とフローリングの間に結露が発生します。 そんな結露と寝汗がこもった布団を敷きっぱなしにすると、 湿気を除去できないので布団と […]
「 中古品は、製品情報を十分に確認しましょう。 」

最近、業者による販売だけでなく、ネットを介した個人売買などにより 中古品を入手する手段が増えたためか、 新品を購入する前に中古品をチェックする、という方が増えているとか。 家づくりのため、少しでも出費を抑え […]
【 退職金を当てにした返済計画は危険です。 】

住宅ローンの借入額を決める時、 教育費や老後資金を貯蓄しながらでも定年までに無理なく返済できる 『返済可能額』の範囲内に設定した方が安心です。 しかし、業者によっては 「定年までに完済できなくても、退職金で […]
[[こんなときどうするの?…重大事故が発生しているリコール製品]

今日は、『重大事故が発生しているリコール製品』についてです。 平成29年度に報告されたリコール対象の重大製品事故のうち、 ・パナソニック「ノートパソコン用バッテリーパック」 ・東芝「ノートパソコン用バッテリ […]
[[こんなときどうするの?…凍害]]

今日は「凍害」についてです。 凍害とは、外壁に入り込んだ水分が凍結や融解を繰り返すことで、外壁がひび割れたり剥がれたりする現象のことです。 外壁の継ぎ目や表面の経年劣化を放置すると、水分が入り込みやすくなります。 水分が […]
[[こんなときどうするの?…近隣への挨拶]]
今日は、近隣への挨拶についてです。 新築工事と同様に、リフォーム工事にも騒音や粉じんが発生します。 職人や専門業者の車が出入りも増え、近隣の方には少なからず迷惑を掛けることになります。 近隣の方のことを思うなら、工事前の […]
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (9)
- 2025年9月 (9)
- 2025年8月 (9)
- 2025年7月 (9)
- 2025年6月 (8)
- 2025年5月 (8)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (7)
- 2025年1月 (9)
- 2024年12月 (9)
- 2024年11月 (7)
- 2024年10月 (9)
- 2024年9月 (8)
- 2024年8月 (9)
- 2024年7月 (9)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (9)
- 2024年4月 (9)
- 2024年3月 (9)
- 2024年2月 (8)
- 2024年1月 (9)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (8)
- 2023年10月 (9)
- 2023年9月 (9)
- 2023年8月 (9)
- 2023年7月 (8)
- 2023年6月 (9)
- 2023年5月 (9)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (8)
- 2023年1月 (8)
- 2022年12月 (9)
- 2022年11月 (9)
- 2022年10月 (8)
- 2022年9月 (9)
- 2022年8月 (8)
- 2022年7月 (9)
- 2022年6月 (8)
- 2022年5月 (9)
- 2022年4月 (9)
- 2022年3月 (9)
- 2022年2月 (8)
- 2022年1月 (8)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (9)
- 2021年10月 (9)
- 2021年9月 (8)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (8)
- 2021年6月 (7)
- 2021年5月 (8)
- 2021年4月 (8)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (9)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (9)
- 2020年9月 (9)
- 2020年8月 (8)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (7)
- 2020年5月 (9)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (8)
- 2020年2月 (7)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (9)
- 2019年11月 (7)
- 2019年10月 (9)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (8)
- 2019年7月 (8)
- 2019年6月 (8)
- 2019年5月 (9)
- 2019年4月 (9)
- 2019年3月 (9)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (7)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (8)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (8)
- 2018年6月 (9)
- 2018年5月 (9)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (9)
- 2017年12月 (9)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (8)
- 2017年9月 (9)
- 2017年8月 (8)